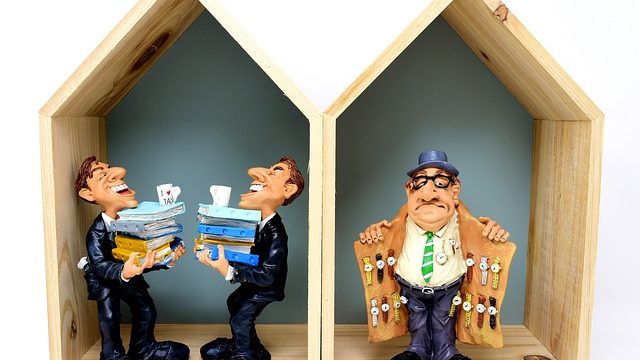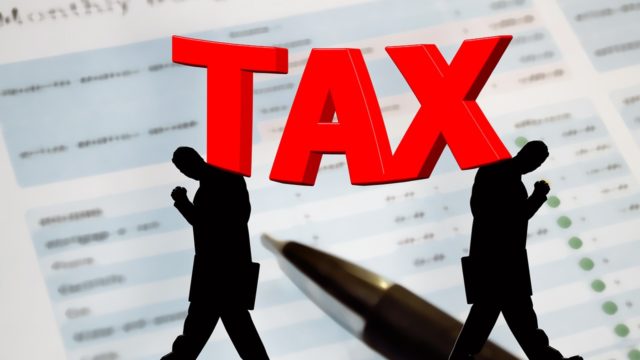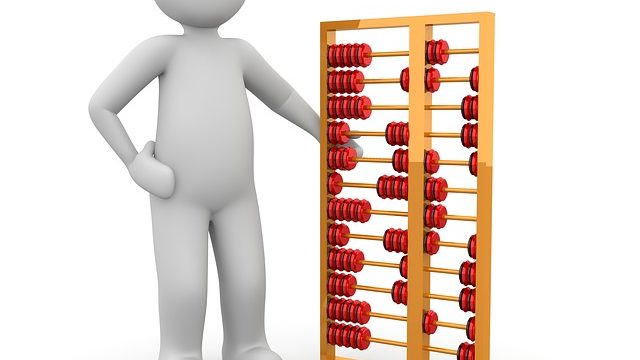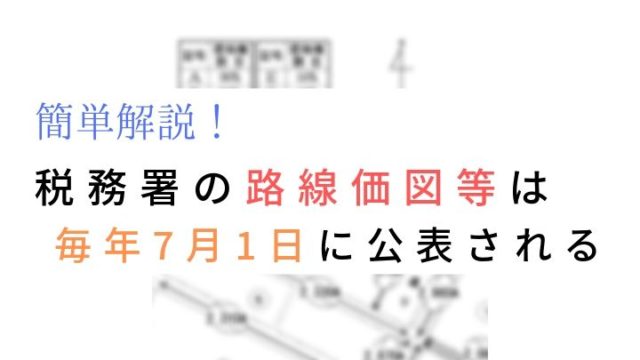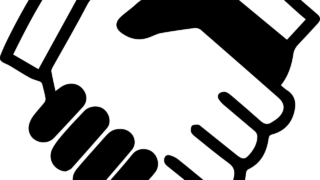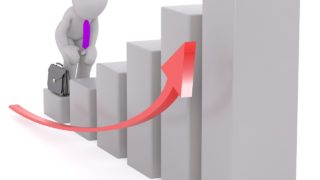相続税は、富裕層の方に対して課される税金だと思っていませんか。
相続税は『サラリーマン家庭』と呼ばれるような会社員・公務員のご家庭でも対象となる税金です。
私の父は年金暮らしだったし大丈夫。
私の夫はサラリーマンだったし、今そんなに貯金も無いから関係ないよね。
と、考えて税務調査を受けるケースは少なくありませんので、本記事で相続税の基本的な知識を身に付けてください。
※ この記事では亡くなった人を被相続人と表記いたします。
1:相続税は必ず申告すべき税金ではない
相続の経験をした方は少なくないと思いますが、相続税の申告手続きの経験をした方は限られます。
なぜなら相続税は課税対象になる人と、ならない人に区分され、9割の方は相続税の申告が不要な方に該当するからです。
⑴ 相続税は基礎控除以内の財産なら申告不要
相続税は相続人全員が判断する必要はあります。
しかし、全ての人が必ず申告する必要はありません。
相続税には基礎控除額があり、相続財産が相続税の基礎控除額以内であれば相続税は発生しません。
【相続税基礎控除額の計算式】
3000万円+600万円×法定相続人の人数=相続税基礎控除額
たとえば相続人が3人いるご家庭であれば、基礎控除額は4,800万円となりますので、4,800万円を超える相続財産が無ければ、相続税は無税となります。
・ 相続人が配偶者と子2人の場合
3000万円+600万円×3人(配偶者と子2人)= 4800万円
また相続税が発生しない場合、税務署に相続税の申告書の提出は不要となりますので、は不要となります。
⑵ 相続税の申告期限は相続開始日の翌日から10か月以内
相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合、相続税の申告が必要となりますが、申告期限は相続開始日(亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
また相続税の申告期限は納付期限でもありますので、納税額が発生している方については10か月以内に納税も済ませなければなりません。
相続税の申告書を提出する場所ですが、被相続人の住んでいた場所を管轄する税務署です。
たとえば相続人が千葉県柏市(柏税務署管轄)に住んでいたとしても、被相続人が北海道函館市に住んでいた場合、申告書の提出先は函館税務署となります。
※ 被相続人が海外で亡くなった場合にはケースが変わる可能性がありますので、最寄りの税務署に確認してください。
⑶ 相続税の課税対象となる人は1割未満
住んでいる地域によって相続税の申告書を提出する割合は異なりますが、亡くなった人のおおよそ6~8%が相続税の対象となります。
東京都の中心部であれば、1割以上の方が申告手続きをする一方、地方については課税割合が下がります。
2:法定相続分は相続人の立場によって異なる
相続税の基礎控除額を計算する場合、法定相続人の数を特定しなければなりません。
また相続財産を分けるとなった場合、相続人の続柄によって法定相続分が変わってきます。
⑴ 配偶者(妻、夫)は必ず相続人となる
配偶者は法律上(民法)特別な位置にあり、法定相続分は最低でも1/2あります。
日本の法律上、戸籍上の配偶者のみしか配偶者として認められていませんので、いわゆる『事実婚』は相続権がないのでご注意ください。
また配偶者の法定相続分は、配偶者以外の相続人の続柄によって変化します。
・ 法定相続分
民法上で定められている相続する権利の割合
・相続人が配偶者と子の場合の相続権の割合
配偶者 1/2
子 1/2
・相続人が配偶者と被相続人の親の場合
配偶者 2/3
親 1/3
・相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合
配偶者 3/4
兄弟 1/4
配偶者は、最低でも相続財産の半分は相続できる権利があり、子や兄弟が相続人の場合は同じ立場の人の人数(子なら子の人数)によって自分の相続できる権利が少なくなります。
民法(法定相続分)第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
⑵ 相続人の第一順位は子
相続人の承継順位の第1位は子になります。
(配偶者は他の相続人の存在に関わらず法定相続人です。)
子には養子も含まれるため、被相続人の娘と娘婿(養子縁組)していた場合には相続人は2人です。
また、民法上は子の生まれた順番での相続権の差はなく、3人兄弟であれば3人平等に権利は存在します。
・相続人が配偶者と子3人(A、B、C)の場合
配偶者 1/2
子A 1/2×1/3(子3人)=1/6
子B 1/2×1/3=1/6
子C 1/2×1/3=1/6
※ 以前は子によっても相続割合が違っていましたが、平成25年9月4日の最高裁で子の相続権は一律平等との判決が下されました。
⑶ 子がいない人は両親が相続人に
被相続人に子がいない場合には、被相続人の両親が相続人となります。
法律上は直系尊属といい、両親が先に亡くなっている場合、相続権は祖父母に移ります。
・直系尊属
自分の直通する血族
自分の両親、祖父母、曾祖父母が該当する。
※配偶者の両親は直系尊属ではないが、養子縁組をした養父母は直系尊属に該当する。
・ 相続人が配偶者と被相続人の父Dと母Eの場合
配偶者 2/3
父D 1/3×1/2(DとE)=1/6
母E 1/3×1/2=1/6
⑷ 両親がいない場合には兄弟が相続人に
被相続人に子も両親(祖父母)もいない場合、法定相続人は被相続人の兄弟です。
兄弟の場合は被相続人の子の場合と異なり、被相続人と両親が同じかどうかで相続権の割合が変わります。
・ 全血兄弟
被相続人と同じ両親の子である兄弟
・ 半血兄弟
被相続人と両親が片方のみ同じである兄弟
相続人に全血兄弟と半血兄弟がいる場合法定相続分の割合は2:1となります。
・相続人が配偶者と全血兄Fと半血弟Gの場合
配偶者 3/4
兄F 1/4×1/3×2(2:1の2)=1/6
弟G 1/4×1/3×1(2:1の1)=1/12
⑸ 相続権利を承継する代襲相続について
被相続人よりも先に子が亡くなった場合には親が第2相続順位になりますが、先に亡くなった相続人の子に子(被相続人の孫)がいる場合、その人が相続人の地位を引き継ぎます。
法律上では代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、被相続人よりも先に亡くなった相続人の子に相続権を承継します。
子の子が複数いる場合には本来の子の権利を分けることになるので、代襲相続人以外の相続人の法定相続分がが減少することはありません。
・相続人が配偶者と子Hと子Rの子J、Kの場合
(子Rは被相続人より先に死亡)
配偶者 1/2
子H 1/2×1/2(子H、Rの人数)=1/4
Rの子J 1/2×1/2×1/2(子の子J、Rの人数)=1/8
Rの子K 1/2×1/2×1/2=1/8
被相続人の兄弟が先に亡くなっている場合も代襲相続の対象となりますが、子の場合との相違点は代襲の回数です。
被相続人の子の場合には代襲相続を2回できます。(再代襲)
被相続人から見ると、子と孫が先に亡くなっても曾孫がいれば曾孫が相続人になります。
被相続人の兄弟の場合には代襲相続は1回だけです。
被相続人よりも先に兄弟が亡くなっている場合には兄弟の子は代襲相続人になれますが、兄弟の子も亡くなっている場合には兄弟の子の子(孫)は相続人にはなれません。
3:相続税の対象となる財産
相続税は亡くなった人が保有していた全てが課税対象となります。
⑴ 基本的に被相続人の全財産が相続税の課税対象
基本的に被相続人が所有していた財産は全部相続税の課税対象です。
お墓など、非課税財産も一部存在しますが、相続税の申告の有無を確認する場合は全財産が基礎控除額を超えるか否かをチェックしてください。
<主な相続財産の種類>
- 現金
- 預貯金
- 不動産(土地、建物)
- 株式
- 車
- 貴金属
- 貸したお金(債権)
⑵ 借金などのマイナス財産は控除対象
借金やお葬式の費用は相続税の扱い上、債務(減額対象)となります。
相続税の計算ではプラスの財産からマイナスの財産の残りが基礎控除額を超えるかで判断しますので、1億円分の土地を所持してても、2億円借金があれば相続税は発生しません。
1億円ー2億円=0円(マイナスは0円扱い)
ただし、相続人Aが1億円の土地を相続し、相続人Bは借金2億円を相続した場合には、Aさんに相続税が発生する可能性があるので注意が必要です。
⑶ 相続財産ではなくても相続税の対象となる財産
相続税は亡くなった時点の被相続人の所有していた財産が対象となりますが、例外があります。
それが、死亡保険金と死亡退職金です。
ざっくりとした考えでは、保険金や退職金を受け取る原因が被相続人の死亡の場合には相続財産と合算して相続税の計算をします。
相続財産が預貯金1000万円のみであったとしても、死亡生命保険金が1億円ある場合には相続税の対象金額は1億1000万円となり、相続税が発生します。
ただし、死亡保険金と死亡退職金には別途控除額があり、受け取った金額が各控除額以内に収まる場合、相続税の対象となる金額は0円です。
・ 保険金控除・退職金控除の計算式
500万円×法定相続人の人数=それぞれの控除額
※控除額を超える場合には超えた部分が相続税の対象
※この控除が適用できるのは法定相続人のみ
4:相続が発生したら被相続人の財産をすべて把握すること
相続税の申告期限は、相続開始日(亡くなった日)の翌日から10か月以内ですので、できるだけ早く相続財産を把握するようにしてください。
相続財産が相続税の基礎控除額以内であれば相続税は0円ですので、ゆっくりと遺産分割協議をしても相続税の納税額が増えることはありません。
一方で、基礎控除額を超える財産があった場合、期限内に申告手続きをしなければいけません。
申告期限を過ぎてしまうと、適用できない優遇制度やペナルティーの税金が発生しますので要注意です。
私は税務署で相続税担当をしていましたので、
- 相続税があるとは知りませんでした
- 相続税が発生するとは思っていませんでした
という相続人の方を、何人も見てきました。
税金関係は知らなかったが通用しませんので、いかに早く相続財産の全体を把握するのかが鍵となります。
相続が発生するまでに財産状況を調べていれば相続対策も講じられますので、相続税の基礎控除額やざっくりとした相続財産の金額はチェックしておいた方がいいでしょう。
ご参考になれば幸いです!